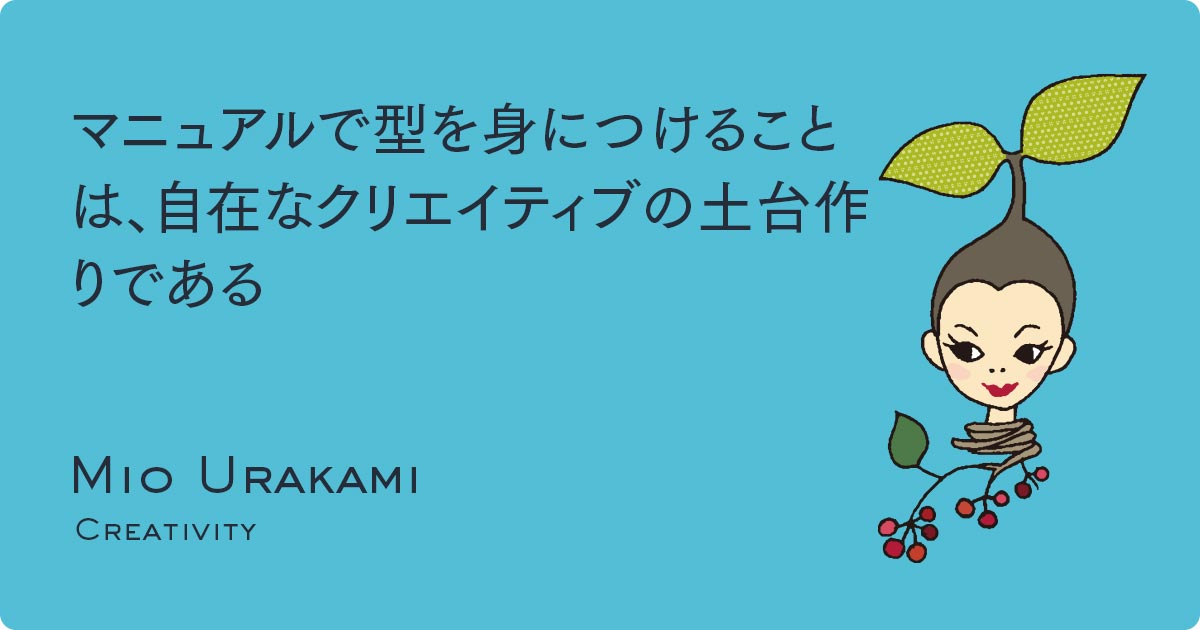「マニュアル通り」「マニュアル人間」…のように使われる場合、あまり歓迎されない存在として扱われがちなマニュアル。
クリエイティブなことをやりたい人にとっては、その存在が少し鬱陶しいものだったりもするマニュアル。
であるけれど、よくできたマニュアルは、人の可能性をおおいに広げてくれる便利なツールである、と私は思っています。
その根拠を、我が家で作るソース焼きそばで説明します。
この焼きそばは、昔のテレビ番組、「ためしてガッテン」で紹介されていたレシピで、様々な実験や試行錯誤の元に完成したレシピとのことでした。このレシピで作る焼きそばが私は大好きで、いままでに何度も繰り返し作ってきました。
以下の手順で作ります。(蒸し麺の焼きそばです)
- 火をつけていないフライパンにサラダ油をひく。
- 麺をそのまま乗せてから火をつけ、中火で2分加熱する。
- 麺をひっくり返したらフライパンの開いているところで豚肉を焼く。
- 豚肉が焼けたらキャベツを麺の周りに乗せる。(この間1分)
- 熱湯を麺にかけるように入れすぐにフタをして強火にし、1分30秒加熱する。
- パチパチ音がしたらフタを開け火を止めて、ソースをかけて混ぜたらできあがり。(この間30秒)
2分とか1分とか1分30秒のところは適当にしないで律儀にタイマーをかけてきっちりその通りの時間で作ってみたところ本当に美味しかったので、その後何度も同じようにして作りました。
何度も作っていると、だんだん、麺を載せて火をつけて2分後の香りや音はこのくらい、とか、強火にして1分30秒後の音は大体このくらい、というのを鼻や耳で覚えてくるんですね。そうなれば、もうタイマーはいらなくなる。頭で考えなくても、身体が覚えてくれている感じ。
これこそが「型」が身についた状態です。
そうすると、ちょっと作り方アレンジしてみようかなとか、具材を違うの使ってみようかな、とか、なんなら焼きそばじゃなくて、うどんやパスタでもやってみようかな、などと考える「脳みそのゆとり」がでてくるんですね。ちゃんと基本の美味しさを保ったまま、そういうアレンジをチャチャっと施すことができるようになる。
つまり、この「脳みそのゆとり」を最大限活用することで、クオリティを保ったままあたらしい展開をいろいろ生み出すことができるようになる。
マニュアルで身につけた型が、クリエイティブのしっかりした土台になるというわけです。
これは、物を作る人間にとって大事なポイントなんじゃないかな、と思うのです。
どんなマニュアルがよいマニュアル?
よくできたマニュアルだからこそ、それをきちんと習得することで脳みそにゆとりができ、そこから様々にクリエイティブに発展させていくことができる。
なのですが。このマニュアル、万人に合うものはない、と私は思っています。
誰かがいいと言っているものが、必ずしも自分に合うとは限らない。
なぜなら、人によって「認知のタイプ」が様々だからです。
なので、一つのマニュアルだけを見るのではなくて、いろいろなマニュアルを見て、自分にぴったりくるものをさがすことも、とても大切だと思います。
あるいは、既存のマニュアルを元に、自分なりに理解しやすいようにアレンジしてみる、補足をいれるなどの工夫をしてみるのもよいかもしれません。
認知のタイプって何?
認知のタイプ。そもそも認知って何でしょう?
いくつかの本を読んで私が理解した範囲で言うと「見たり聞いたり読んだりしたことを、それがそれであると理解して自分のものにすること=認知」であります。
例えば「さくらんぼ」という言葉を聞いた時。
すでにさくらんぼを何らかの形で認知しているひとなら、「甘くて酸っぱい果物である」「ジャムにしたり、コンポートにしたりすると美味しい」「6月ごろお店に並んでいて、桐の箱に入っているのはとても高い」というようなことを思い浮かべるでしょう。
「赤くて2〜3個が房になったかわいい形の写真、あるいはイラスト」「パックに入ってお店の果物売り場に並んでいる様子」「クラシックなタイプのパフェの一番上に乗っている様子」などが、画像として脳裏に浮かぶひともいるかもしれないし、子供の頃家族で出かけた、さくらんぼ狩りの思い出が、映像としてよみがえる人もいるかもしれません。
大塚愛さんの「さくらんぼ」のメロディが脳内で再生される人もいるかもしれないし、「さくらんぼ=チェリー」の連想で、スピッツの「チェリー」が脳内再生されるひとだって、いるかもしれません。
とまあ、こんな風に「さくらんぼ」という単語ひとつ取っても、人によって浮かぶイメージ(認知されている情報)は様々なわけです。
そこを詳しく調べていくと、人によって「得意な認知」「苦手な認知」があることが分かるそうです。
例えば私は、何かを学習するときにはストーリー形式になっているものが好みです。必要な内容が物語仕立てになっていることで、自然にすっと頭の中に入ってきて定着してくれるんですね。
でも、夫は逆で、ストーリーになっているとかえって理解が妨げられるので、解説書的なものの方がよいと言います。
他にも、映像で見るのが一番理解できる人や、音声で聞くのが理解できる人など、人によってタイプが違うようなので、自分にぴったりくるマニュアルを見つけるためには、ざっくりとでも、自分がどのタイプなのかを分析して知っておくのがよいかもしれません。
本田真美さんという、子供の発達を専門にされているお医者さんの書かれた「医師の作った頭のよさテスト」という本の中に認知の特性テストというのが入っているのですが、オンラインでも認知特性をチェック出来るページがありました。リンクを貼っておきます。
レビューで賛否両論がある本が狙い目?
Amazonなどネットショップで売られているマニュアル本のレビューを見てみると、賛否両論がある本ほど、何らかの認知のタイプに偏った本の可能性があるように思います。その内容がすごくフィットする人がいる一方で、全然合わない人もいる。それはその本の内容に問題があるのではなくて、合う・合わないの問題で、その本がぴったりフィットする人にとっては、またとないよいマニュアル本になるだろうとも思うのです。
それについては「自分の育て方について」という記事にも書いたので、よかったらそちらもご覧くださいね。
まとめ
そんなわけでマニュアルについて。マニュアルを通して型を身につけておくことは、大いにクリエイティブの助けになるかもよ?という話でした。
これだ!というマニュアルをきめたなら、しつこいくらい、反復練習をすること。
マニュアルを見なくても完璧にできるようになったら、考えなくても手が動くようになるから、そうなったらしめたもの。
そこからが、自分独自の「何か」を生み出すための第一歩です。考える脳みそのゆとりをフル活用して「その先の世界」をたくさん開拓していけますように!